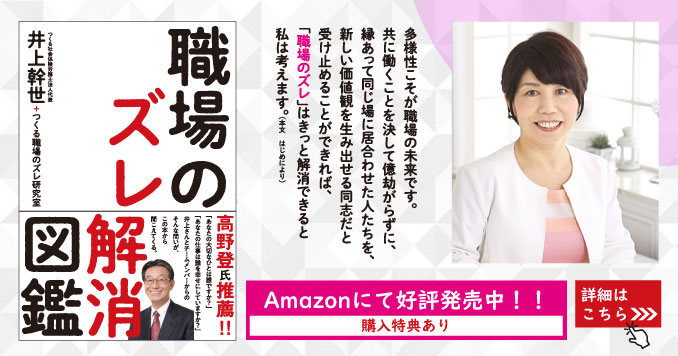About us
企業の伴走者として
「共に成長する」
お客様をはじめ関わるすべての皆様と「共に成長する」ことを使命とし、社員一同、謙虚な姿勢で学び、お預かりした業務に全力を尽くすことをお約束いたします。
- 作る
- 働きやすい仕組みを作る
- 造る
- 認め合い磨きあう組織を造る
- 創る
- 新しい仕事の概念を創る
- Too Cool
- 輝くビジネスパーソンをつくる
日々加速する社会変化に、企業も個人もその対応に追われる激しい時代です。人工知能の目覚ましい発展によって、事務手続や情報管理は効率化・省力化されていきますが、人と人、心と心の関係は、ぬくもりある人間同志でしか築くことができません。そのような繊細かつ重要な関係構築のサポートをするのが、私たち「社会保険労務士」です。会社は「人と仕事を育てる場」であると考えます。その想いを新しい法人名『つくる』に込めました。
Service サービス案内
News 新着情報
ニュース&コラム
-
2024.03.29
お知らせ - 「健康経営優良法人2024(中小規模法人部門)」に認定されました!
-
2023.12.25
お知らせ - 採用情報更新しました
-
2023.12.16
お知らせ - 年末年始休業のお知らせ